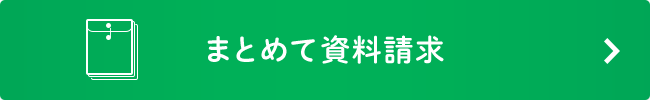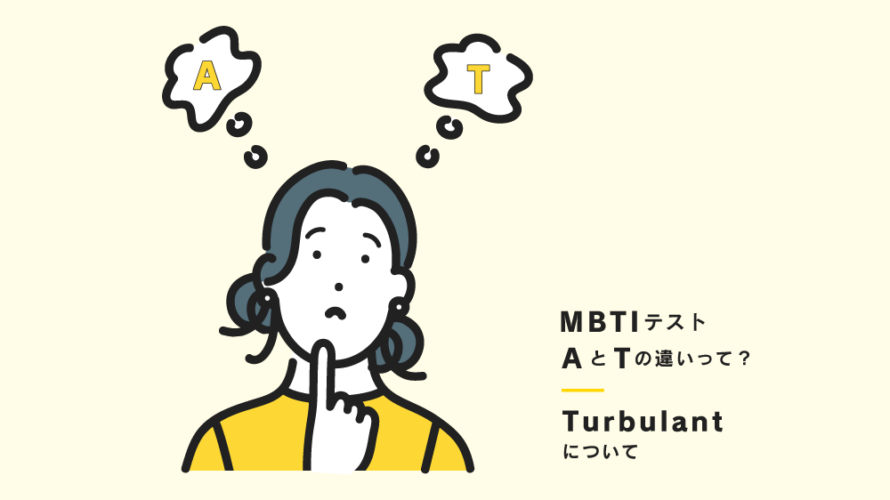救命救急士になるには
- 2020.01.29


救命救急士の概要や仕事内容
救命救急士とは?
救急救命士は救急車に同乗するなどして傷病人が病院に搬送されるまでの間、傷病者に対して「救急救命措置」を行う仕事です。救命救急士は国家資格です。
また、救命救急士の多くは消防署などに勤務するそうなのですが、消防署に勤務するためには地方自治体の消防本部などが行う消防士採用試験(公務員試験)に合格する必要があります。
つまり消防署に勤務している救命救急士は国家資格を持ちながら働く地方公務員ということになります。消防官になった後で救命救急士の国家資格を取得する消防官もいます。
病気や怪我には命に関わるものとそうでないものがありますが、救急救命措置は迅速に処置をしなければ死亡してしまう「心停止」などの命に関わる傷病者を含む重病者に対して行われます。
人の命を扱うかなり責任の重い仕事ですが、病院に到着するまで命をつなぐ大切なお仕事です。
救命救急士の仕事内容とは?
救命救急士法第43条第1項に
「救急救命士は、保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として救急救命処置を行うことを業とすることができる。」
と記載されています。
保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条の規定というのは看護師などが医師に対して行える「診療の補助」を、看護師でないものが行ってはいけないという規定です。これを救命救急士法第43条第1項によって、診療の補助を行ってもよいと規定しているのです。ただし、医師の指示がなければ救急救命措置を行ってはならず、原則として救急車以外での業務を行ってはいけません。
救急救命処置は次の範囲で行われます。
●医師の具体的な指示で行うもの(特定行為)
- 乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保
(心肺機能停止状態または呼吸機能停止状態の患者) - 器具を用いた気道確保(心肺機能停止状態の患者)
- 薬剤の投与(心肺機能停止状態の患者)
- 乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保及び輸液
(心肺機能停止状態でない重度の患者) - 低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与(心肺機能停止状態でない重度の患者)
●医師の包括的な指示で行うもの( 重度の患者に対して行います)
- 自動体外式除細動器(AED)による除細動
- 精神科領域の処置
- 小児科領域の処置
- 産婦人科領域の処置
- 自己注射が可能なエピネフリン製剤によるエピネフリンの投与
- 血糖測定器を用いた血糖測定
- 聴診器の使用による心音・呼吸音の聴取
- 血圧計の使用による血圧の測定
- 心電計の使用による心拍動の観察及び心電図伝送
- 鉗子・吸引器による咽頭・声門上部の異物の除去
- 経鼻エアウェイによる気道確保
- パルスオキシメーターによる血中酸素飽和度の測定
- ショックパンツの使用による血圧の保持及び下肢の固定
- 自動式心マッサージ器の使用による体外式胸骨圧迫心マッサージ
- 特定在宅療法継続中の傷病者の処置の維持
- 口腔内の吸引
- 経口エアウェイによる気道確保
- バッグマスクによる人工呼吸
- 酸素吸入器による酸素投与
- 気管内チューブを通じた気管吸引
- 用手法による気道確保
- 胸骨圧迫
- 呼気吹き込み法による人工呼吸
- 圧迫止血
- 骨折の固定
- ハイムリック法及び背部叩打法による異物の除去
- 体温・脈拍・呼吸数・意識状態・顔色の観察
- 必要な体位の維持、安静の維持、保温
救命救急士になる方法(資格取得方法等)
救急救命士の国家試験の受験資格は次のように定められています。
・大学に入学することができる者であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した救急救命士養成所において、2年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得した者。
・大学若しくは高等専門学校や養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した救急救命士養成所において、1年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得した者。
・大学(短期大学を除く)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者。
・消防法第2条第9項に規定する救急業務に関する講習を修了し、及び5年(救急活動を行った時間が2,000時間に至った場合においては、それまでの間に救急業務に従事した期間)以上救急業務に従事した者であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した救急救命士養成所において、1年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得した者。
などです。割愛している部分がありますが、簡潔にまとめると指定の学校で2年以上学ぶ、専門科目を1年以上+学校などで1年間専門知識を学ぶ、救急業務に決められた年数(または時間)従事+1年以上専門知識を学ぶ…といった感になります。
では、消防官になる方法と、養成学校を卒業する方法に分けてみていきましょう。
①消防官になる
高校以上の学校を卒業した後、自治体の消防士試験を受験・合格したのちに消防官になり、救急隊員として5年以上もしくは救急活動を2,000時間行うなどして実務経験を積みます。その後救命救急士養成所にて1年以上(特定の条件を満たす養成所については6か月以上)で学びます。
これによって救命救急士国家試験の受験資格を得ることができます。
ただし、消防官になってすぐに救急隊員として勤務できるかといわれると、所属する自治体の規模や条件によります。たとえば小規模の自治体であれば消火活動も救急も行うことが多いため、早くに救急隊員としての仕事を行うことができる可能性があります。また、「採用後○年間は消防官としての実務を経験する」としている自治体もあります。
②養成所を卒業する
高校卒業後、厚生労働大臣が指定した養成所を卒業して受験資格を得る方法です。
救命救急士の養成所には大学や短大、専門学校などがあります。そこで2年以上救命救急士として学ぶことで国家試験の受験資格を得ることができます。(ただし、大学で1年以上の過程を修了している場合には1年間の学習で受験資格を得ることができます。)
一日も早く救命救急士として働きたいという場合、消防官になってから救命救急士の国家試験を受けようとすると長期間かかってしまう可能性があるため、2年間専門学校の救命救急士学科などで学び、卒業後に救命救急士の国家試験に合格し、消防士試験に合格するルートのほうが早い可能性が高いということになります。
仮に消防官の実務を3年しなければならないとしても、消防官スタートの場合は消防官実務3年+救急活動5年+養成所で1年修業とすると9年かかることになりますが、学校スタートだと(国家試験と公務員試験をダブル受験した場合)専門学校2年+消防官実務3年=5年で救急隊員になれる可能性があるからです。
資格難易度や試験について
試験について
救命救急士の国家試験は毎年3月上旬頃行われます。
合格率はここ数年85~90%程で、決して低くない数字だと言えますが、同じように学校に通うなどして受験する看護師の合格率が例年90%近いことと比べると少し低めです。
●試験の概要
※下記は2020年度の試験の日程です。
受験書類の配布:2019年10月15日(火)~
一般財団法人日本救急医療財団に郵送で請求することができます。
受験書類の受付:2020年1月6日(月)~2020年1月24日(金)までに、
一般財団法人日本救急医療財団へ書留郵送で提出します。
直接提出することも可能です。
試験日程:2020年3月8日(日曜日)
試験地:北海道、東京都、愛知県、大阪府、福岡県
試験科目:
(1)基礎医学(社会保障・社会福祉、患者搬送を含む。)
(2)臨床救急医学総論
(3)臨床救急医学各論(一)(臓器器官別臨床医学をいう。)
(4)臨床救急医学各論(二)(病態別臨床医学をいう。)
(5)臨床救急医学各論(三)(特殊病態別臨床医学をいう。)
合格発表:2020年3月31日(火)
今後の救命救急士の将来性
救急車の出動件数は年々増加しています。
そしてその救急車に最低1人は救命救急士を乗車させることが目標とされています。
「目標とされている」、つまり不足しているということになります。
さらに言うと、高齢化により救急車の出番が増えているだけでなく、民間の介護施設や搬送会社、人が集まる施設などにも救命救急士の求人があるのです。
救命救急士が不足している現状からしても、この先救命救急士の需要が減ることはしばらく考えられないでしょう。そのため、十分に将来性があるといえます。
救命救急士の就職先
正確な数字は発表されていませんが、約6割の救命救急士は消防官として働いているようです。
その他の救命救急士は次のような就職先で活躍しています。
- 海上保安庁
- 警察
- 自衛隊
- 病院
- 民間搬送会社
- 警備会社
- 介護老人保健施設
このように、救命救急をすぐに行うことができる救命救急士を必要としている機関がたくさんあるのです。
救命救急士に向いているのはこんな人
救命救急士は人の生死にかかわる場面が多いため、常に冷静に状況を判断し、処置を行っていかなければなりません。
人の命を救いたいという強い気持ちはもちろんのこと、常に冷静沈着でいられることが求められるでしょう。
また、いつどこで出動要請があるかわからないので体力が必要で、患者さんの姿が見るに堪えない場面に遭遇することにもなるため精神的な強さも必要です。
医療はチームで行うため、高いコミュニケーション能力も大切です。
そして、日々医療は進歩し続けています。
常に新しい知識を身に着けていられる勤勉さも重要です。
冷静沈着で、肉体的・精神的なタフさを持ち、コミュニケーション能力が高く、勤勉である人が救命救急士に向いているということになります。
救命救急士に関連する職業や資格
関連する職業
●消防官
ここまで述べてきたように多くの救命救急士は消防官として就職しています。
消防官の知識も得ることになるため、消火活動や救助隊としても働くことができます。
●医療従事者
医師の指示が必要になることや、搬送先の病院で看護師などに患者さんのデータを引き継ぐことなどから、医療従事者とはしっかりとコミュニケーションをとっていかなければなりません。
-
前の記事


インテリアプランナーになるには
-
次の記事


空間デザイナーになるには


 専門学校を探す
専門学校を探す