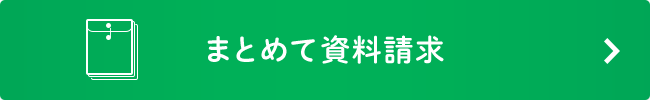大学の4年制でもなく多くの専門学校が設く2年制でもありません。桑沢デザイン研究所の昼間部は、3年制の独自のカリキュラムを行っています。
3年間をかけて、デザインの基礎の基礎から、社会で役立つ考え方と技術まで、幅広く学んでいきます。
- 卒業後の主な進路
-
- エディトリアルデザイナー
- ファッションデザイナー
- テキスタイルデザイナー
- パタンナー
- インテリアデザイナー
- 空間デザイナー
- グラフィックデザイナー
- パッケージデザイナー
- フォトグラファー
- 修業年限
-
3年
- 初年度納入金
-
1,580,000円
1年次では全員が共通の基礎を学び、眠っている感性を呼び覚まします。2年次からは専門分野に分かれて、それぞれの知識・技術を身につけていきます。そして、3年次にはそれらの応用を積み重ねることで、デザインに必要な観察力・発想力・構成力を豊かに培っていきます。
いまデザイン教育の現場では、即効性だけを重視し、テクニックに力点が置かれています。しかし、いきなり技術を教えることは、デザイナーとしての未来に限界をつくることになりかねません。これからの長い将来へ向けて、デザインの基礎体力を強化することが、今もっとも求められていることなのです。
デザインは「人の暮らしを豊かにするため」にあります。時代がどう変わっても、社会に貢献できるデザインの根本的な力を身につけること。これが〈桑沢〉の理念であり、目指している教育です。
【1年次 共通課程】
「基礎造形」と「基礎デザイン」二つの基礎を通じ「デザインとは何か」を学ぶ
1年次では専門分野を学ぶ前に、「デザインとは何か」を徹底的に考えていきます。そのためにすべての学生が同じ科目に取り組みます。
デザインには技術だけでなく、それを裏づける論理的な思考が必要です。〈桑沢〉が重視しているのは、「手を動かしながら考える」こと。既成概念を疑い、ものごとを深く観察し、自らの頭で考えることで、新たな発想を生み出す力を身につけていきます。
専攻・コース一覧
-
ビジュアルデザイン専攻

一過性の風潮や流行ではなく、人間が本来もっている根源的な要素を基盤とした「視覚情報とは何か」を考える
広告や雑誌、スマートフォンの画面など、現代に生きる私たちは視覚情報に囲まれています。一過性の風潮ではなく、人間がもつ根源的な要素とは何か。情報あふれるなかで、メッセージを伝える対象は誰なのか。また、それをどのように伝えればいいのか。適切な表現方法やメディアとは。こういった普遍的な問題を追究するのが〈桑沢〉ビジュアルデザインの特徴です。
【2年次 身近な問題からデザイン構築の方法を学ぶ】
広告や雑誌、パッケージ、デジタルデザインがあふれる時代。人は視覚情報からどのような感覚的イメージを受け取るのか。メッセージを適切に伝えるための表現方法やメディアとは。こういった普遍的な問題を追究するための基盤として、デジタル技術の基礎をマスターします。またグラフィックデザイン、パッケージやタイポグラフィ、写真やイラストなどの専門知識も身につけ、身近な問題からデザインを構築する方法を学びます。
【3年次 社会に問題意識を持ち、アイデアを提案する】
分析の対象を社会や世界へと拡大し、論理的にデザインを組み立てる思考を養います。どうすれば社会のニーズに応える効果的な表現ができるのか。ゼミナールでは、ひとつのテーマを1年かけて追及し、作品の完成度を高めていきます。「人や社会の豊かさとは何か」という問題意識を持ち、アイデアを具体化して提案できるデザイナーへ。それを目標にして、視覚情報を的確に美しく、また楽しく伝えられる方法を研究します。
-
プロダクトデザイン専攻

自動車、電気製品などの工業デザインから生活用品まで。環境やコストなど、さまざまな制約を乗り越えるデザイン能力を養う
プロダクトデザインでは、携帯電話や文房具、自動車やキッチン用品など、量産されている、目に見えるものすべてが対象となりす。人々はその製品を選び、使うことを通して、その人らしく暮らし、生きています。つまりプロダクトデザインには、人間の意識や哲学を変えることのできる力が秘められているといえます。そして、プロダクトデザイナーは、私たちが生きる社会に対して、あらゆる責任を負っているといっても過言ではないでしょう。どんな材料でつくるのか、どのように生産するのか。できあがった製品だけではなく、素材や加工方法など、例えば環境問題にも配慮する必要があります。
【2年次 演習、実習、講義の三本柱で基礎を身につける】
授業の中心は「技術演習」「デザイン実習」「理論講義」。製図やスケッチ、モデリングなどの表現技術とともに、発想力や提案力を養います。後期の課題では、ドライヤーなど具体的なテーマが設定され、デザインにおける一連の過程を体験します。プロダクトの多くは立体物ですが、デザインの検討は、スケッチや図面など平面で行います。そのため2次元と3次元の垣根を自在に行き来する能力が求められます。
【3年次 視野を広げ、課題を通じて発想力を鍛える】
コスト、環境への配慮、クライアントの意見など、さまざまな制約のなかでの調整力と、細部への気配りが求められるプロダクトデザイナー。視野を広げ、発想力を鍛える課題が増えます。卒業制作では自らの関心に沿ったテーマを設定。担当講師がデザイン指導を行い、専任講師が全体の進行をサポートします。コンセプト決定、ラフモデル制作、最終作品の完成プレゼンテーションなど、社会に出る前の集大成を行います。 -
スペースデザイン専攻

「エレメント」「インテリア」「住環境」から人と空間の関係性を理解し、スペースデザインの可能性を追い求める
「エレメント」「インテリア」「住環境」の3領域を学びます。「エレメント」は、家具や照明からドアノブに至るまで、空間の中に存在するもの、「インテリア」は、主にショップやレストランなどの商業スぺースのインテリアを指します。そして「住環境」では、人の暮らしがある住宅を通して建築設計について学びます
【2年次 場を生み出す「空気」をデザインすること】
家具や照明など空間を構成する単位である「エレメント」、内部空間を意味する「インテリア」、そして我々の住む都市環境を形づくる「住環境」の3つの分野を主に学びます。機能的な要求だけではなく根本的な空間の成り立ちを理解し、人とモノと空間の関わりを深く考えることで、人間にとって豊かで美しい空間とは何かを考えます。また空間をデザインすることは、そこに流れる空気や時間のデザインであることを学びます。
【3年次 空間における人と社会との新たな関係を探求】
空間の発生を根本から考え直す課題が増えます。手を動かし続けると同時に、哲学的に物事を考えることが要求されます。誰のための、何のためのデザインか?空間の本質を理解するために、さまざまな関係性を整理し、社会的な意味を掘り下げながら、スペースデザインの可能性を追究します。またCADの授業は2年次に引き続き3年次でも行われ、図面や模型表現のほか、3次元CGでも表現する技術を身につけます。 -
ファッションデザイン専攻

「着る」という普遍性を見据えてデザインを展開する。基礎を固めたうえで、枠にとらわれない自由な発想を目指す
ファッションデザインとは : 身にまとうもの(衣服)のデザインのことを指す。
文化や意識の反映だけでなく、衣服には目的や用途により求められるものが変わる。ファッションデザインには、そうした視点も欠かせない。
【2年次 想像力と個性を引き出すための知識と技術】
自由に発想を広げていくことを目標に、イメージを形づくる訓練を行います。大切なのは基礎を固めたうえで個性を発揮すること。そのための知識と技術を学習します。服の種類からアイテムの構造、素材、平面作図やモデリングの基礎、縫製の技術などを徹底して身につけます。さらに、糸を織ったり編んだりするほか、デジタルを使って生地の柄にする方法を学び、ゼロから発想したオリジナル素材で制作します。
【3年次 客観的な視点から「着る」を多角的に考える】
自分自身の世界観を築き上げ、卒業制作へ向かいます。技術の向上はもちろん、ファッション産業や商品企画を学ぶことで、客観的な視点を養います。さらにブランドの立ち上げ、商品の企画立案、製品化までの流れを実習。企業における展示会までのプロセスを学びます。重要なのは、自己表現の追求とともに、マーケットのニーズを理解すること。ゼミナールでは「着る」という普遍性を多角的に考え、デザインを展開します。